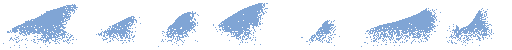
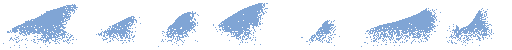
| 定例山行・大津 |
| 日 程 | 2010.12.12(日) | ランク | B |
| 地 図 | 大津 十石峠(国土地理院25000/1) | 天 候 | 晴れ |
| 目 的 | 岩と展望(リーダー育成山行) | ||
| 参加者 | CL:A間Y江(CL)、M原T之(SL)、K島S子、K口S男、K木T郎、I橋W、M田I、 M田N子 総勢 8名 | ||
| 参考タイム |
壬生5:50 -- 8:15大仁田ダムP8:35・・・・9:15取付き・・・・9:45稜線鞍部・・・・ 10:45大津(昼食) 11:45・・・・12:20西峰・・・・12:45 P1053m・・・・13:05稜線鞍部13:40 ・・・・13:55取付き点・・・・14:30大仁田ダムP14:45 -- 19:45壬生 (凡例 → 車又は交通機関、 ・・・歩行)交通手段:マイクロバス | ||
| 投稿者 | M田I、M田N子 | ||
【概 要】 AM8:15大仁田ダムP到着。ストレッチで身体をほぐし、ザックを背負い歩き出す。 ダム湖に架かる橋の先には、西上州特有の急峻な斜面と切り立つ岩肌を持つ山が、深い谷を折り重ねて迫って来る。 *写真をクリックすると大きくなります。 |
|
渓流に沿って南西の方向に山道を進んでゆくと、程なく杉の丸太を三本並べただけの心もとない"橋"が出現、
下を流れる水の勢いに緊張しつつ対岸へ渡る。 途中には、この道がかつて長野県の佐久方面へ抜ける道として 使われていたらしい名残の"馬頭尊"が建っており、酒などがお供えされていた。 さらにその先では、登山道を 何匹もの犬を連れ猟銃を肩に掛けた鹿追いのハンター達とも遭遇した。 |
|
AM9:15一つ目のポイントである"取り付き"地点での休憩後、コンパスを地図上の稜線鞍部に合わせ
急坂を登り始める。ゴロゴロと崩れやすい石が堆積した斜面は、間伐で切倒された木々が放置され道などは
見当らないがここは一気に登りきる。 AM9:45、稜線からは心地良い「陽だまりハイク」に一変。急坂にあえいだ顔もすっかりほころび、 木立の向うに広がる山並を一望しつつ快適に足を進める。尾根道には昔、山の作業で使われたのであろうか、 太いワイヤーロープが沢山放置されていた。 |
|
地図上の1053m地点。ここで尾根はY字となりコンパスで方向を確認して進む。一旦下った後登り返して
左にある岩の頂に登ると、そこには手前の岩が母の背に、覆いかぶさる岩が子に見える"母子岩"? があった。 コースに戻り先を行くと西上州らしい痩せた岩尾根の稜線が出てきた。手前の尾根道にもあったワイヤーロープが、 なぜか登山道や尾根上に架かっていたりする。身をかわしながら進んで行くと、正面に立ちはだかる岩の壁が現れる。 いまにもはがれ落ちそうな岩肌に注意しつつ、立ち木の根や枝も駆使して登る。 |
|
AM10:45「大津」頂上に到着。すばらしい展望は、まさに360度!そして快晴!
手前の鹿岳、後に妙義山。更に奥の赤城山、奥白根。西寄りには白い浅間山、ミドリ岩や荒船方面の山が・・。 こんな気持ちの良い頂上をすぐに降りてはもったいないので、早めではあるが昼食にする。コッフェルとガスが出る、 お湯を持寄るとどこからか具沢山のうどんが出てきた。 全身を使い山の頂上に立ち、おいしい食事と素晴らしい景色を、こうして山仲間と共に楽しめるということは なんと幸せなことだろう。 |
|
AM11:45下山開始。気を引き締め岩の壁を注意深く降りる。帰路は先頭を交代で行くことになり、
1053mの尾根に戻ったところで今日のもう一つのピーク「西峰」へと向かう。 Y字の分岐を北西方向に急降下、そしてまたもや突き出た岩峰によじ登る。ロープなどは一切無いので、 三点確保の基本を忠実に、落石に神経を使いながら全員登頂。ここから「大津」を返り見ると、 山の北壁が深く切れ込んでいかにも凛々しい西上州の岩山だ。 |
|
PM1:40稜線の鞍部。ここから取り付き地点に向かって急坂を下る。
PM1:55取り付きに下山。 木漏れ日が渓流沿いの小道を明るく照らす中、沢の水音を聞きながら、充実感を伴って帰路を踏みしめる。 朝は霜が降りて滑りやすかった丸太の橋は、すっかり乾いて難なく通過できた。 PM2:50大仁田ダムP到着。 |
|
「大津」というあまり山らしくない名の山は、ダム湖に架かる橋の先から静寂な山を渓谷の流れと共にさかのぼり、
明るくおだやかな表情の尾根道と険しい岩の先にたたずむ、とても魅力的な山でした。
|
|
(記録:M田I、M田N子) |